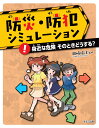「防災・防犯の基本をマンガで楽しく学ぶ!子どもが安全に過ごすための危機管理ガイド」
身近な危険 そのときどうする? (防災・防犯シュミレーション 3) [ 国崎 信江 ] ショップ:楽天ブックス
価格:3,300 円
|
防災や防犯対策は、私たちの生活において欠かせないものとなっています。
特に、家庭における防犯や、子どもたちが日常生活で遭遇するかもしれない危険について考えることは、親にとって重要な課題です。
今回紹介する「防災・防犯シュミレーション3」は、身近で発生しうる危険について具体的に扱った1冊となっています。
この書籍は、子ども向けに危険をわかりやすく解説し、どのように対処すべきかを教えてくれます。
国崎信江氏は、危機管理教育研究所の代表として活躍し、長年にわたりNHKの『くらしの危機管理』のコーナーを担当してきました。
その経験を活かし、子どもたちに分かりやすく危険について学んでもらえるように執筆されています。
この書籍の良さは、現実的で身近な危険についての具体的なシミュレーションを提供する点です。
例えば、留守番中に突然誰かが訪ねてきた場合や、電話がかかってきた場合など、実際に子どもたちが直面しうる状況を題材にしています。
また、公園のトイレでどの個室を使うべきかといった判断についても触れており、日常の中で遭遇する可能性のあるシーンを選んでいます。
このように、とても具体的な状況設定で、子どもたち自身が実際に対処法を考えることができる構成となっています。
本書の中では、防犯対策として日常生活の具体的な状況が取り上げられています。
例えば、車に乗った人が声をかけてきた場合や夜道を歩いて帰る際、どのように自己防衛をすべきかが詳しく記されています。
こうした具体例は、親子で一緒に話し合い、防犯意識を高めるための教材としても優れています。
さらに子どもたちにとって身近な問題であるスマホ・SNSの利用についても詳しく解説されています。
これら現代のテクノロジーは便利である反面、危険もはらんでいます。
SNSへの個人情報の登録や写真のアップロードといった、うっかり見過ごしてしまいがちな問題に対して、具体的なリスクとその対処法がわかりやすく紹介されており、親子でのコミュニケーションツールとしても活用できます。
驚くことに、この書籍の強みの一つは、マンガ形式でストーリーが進む点です。
特に子どもたちの視点で見ると、文字だけの情報はどうしても受け入れにくく感じる場合もありますが、マンガ形式であれば、視覚的に物語を追うことで防犯意識を自然に高めることができます。
マンガの中では、様々なシチュエーションが楽しく、かつ、教訓として描かれています。
これにより、子どもたちは危機管理の重要性を難しく感じることなく、自然に理解していくことができるでしょう。
この書籍は、家庭での防犯対策を考える上で、大変役に立つガイドブックとなります。
親子でこの本を読みながら、日々の危険について話し合うことで、子どもたちの安全に対する意識が高まります。
また、具体的な例を基に、子どもに自主的にどのような行動をとるべきか考えさせることも可能です。
親が子どもと一緒に反復して読んで、何度も危機管理を意識した会話を持つことで、学んだ内容が行動につながっていくのです。
さらに、読み聞かせを兼ねた会話を通じて、家庭内でのコミュニケーションも深まるでしょう。
「防災・防犯シュミレーション3」は学校でも活用できる教材としても最適です。
子どもたちが集まる場所では、どうしても防犯対策が必要不可欠になってきます。
授業中にこの書籍を用いることで、普段の生活に潜む危険性とその対策を学べる良い機会となるでしょう。
また、グループディスカッションの題材として使用することで、児童同士で意見を交わし合うことでさらなる学習となる効果が生まれます。
このプロセスを通じて、実際の状況での適切な判断力を育むことができるのです。
「防災・防犯シュミレーション3」は、国崎信江氏が手がけた、家庭と学校での防災・防犯教育に欠かせない一冊です。
具体的なシナリオを通じて、子どもたちに現実に起こりうる危険を教えてくれるだけでなく、その対応を考えさせる良書となっています。
家庭では親子のコミュニケーションツールとして、また学校では教材として活用することで、子どもたちの危機管理能力を育むサポートをしてくれるでしょう。
この文化的かつ実用的な本を手に取って、皆さんもご家庭や学校で子どもたちと一緒に未来の安全を考えてみてはいかがでしょうか。
特に、家庭における防犯や、子どもたちが日常生活で遭遇するかもしれない危険について考えることは、親にとって重要な課題です。
今回紹介する「防災・防犯シュミレーション3」は、身近で発生しうる危険について具体的に扱った1冊となっています。
この書籍は、子ども向けに危険をわかりやすく解説し、どのように対処すべきかを教えてくれます。
国崎信江が提唱する暮らしの危機管理
国崎信江氏は、危機管理教育研究所の代表として活躍し、長年にわたりNHKの『くらしの危機管理』のコーナーを担当してきました。
その経験を活かし、子どもたちに分かりやすく危険について学んでもらえるように執筆されています。
この書籍の良さは、現実的で身近な危険についての具体的なシミュレーションを提供する点です。
例えば、留守番中に突然誰かが訪ねてきた場合や、電話がかかってきた場合など、実際に子どもたちが直面しうる状況を題材にしています。
また、公園のトイレでどの個室を使うべきかといった判断についても触れており、日常の中で遭遇する可能性のあるシーンを選んでいます。
このように、とても具体的な状況設定で、子どもたち自身が実際に対処法を考えることができる構成となっています。
防犯対策としての具体例
本書の中では、防犯対策として日常生活の具体的な状況が取り上げられています。
例えば、車に乗った人が声をかけてきた場合や夜道を歩いて帰る際、どのように自己防衛をすべきかが詳しく記されています。
こうした具体例は、親子で一緒に話し合い、防犯意識を高めるための教材としても優れています。
さらに子どもたちにとって身近な問題であるスマホ・SNSの利用についても詳しく解説されています。
これら現代のテクノロジーは便利である反面、危険もはらんでいます。
SNSへの個人情報の登録や写真のアップロードといった、うっかり見過ごしてしまいがちな問題に対して、具体的なリスクとその対処法がわかりやすく紹介されており、親子でのコミュニケーションツールとしても活用できます。
危機管理能力を育むためのマンガ形式
驚くことに、この書籍の強みの一つは、マンガ形式でストーリーが進む点です。
特に子どもたちの視点で見ると、文字だけの情報はどうしても受け入れにくく感じる場合もありますが、マンガ形式であれば、視覚的に物語を追うことで防犯意識を自然に高めることができます。
マンガの中では、様々なシチュエーションが楽しく、かつ、教訓として描かれています。
これにより、子どもたちは危機管理の重要性を難しく感じることなく、自然に理解していくことができるでしょう。
家庭での利用法
この書籍は、家庭での防犯対策を考える上で、大変役に立つガイドブックとなります。
親子でこの本を読みながら、日々の危険について話し合うことで、子どもたちの安全に対する意識が高まります。
また、具体的な例を基に、子どもに自主的にどのような行動をとるべきか考えさせることも可能です。
親が子どもと一緒に反復して読んで、何度も危機管理を意識した会話を持つことで、学んだ内容が行動につながっていくのです。
さらに、読み聞かせを兼ねた会話を通じて、家庭内でのコミュニケーションも深まるでしょう。
学校での教材としての可能性
「防災・防犯シュミレーション3」は学校でも活用できる教材としても最適です。
子どもたちが集まる場所では、どうしても防犯対策が必要不可欠になってきます。
授業中にこの書籍を用いることで、普段の生活に潜む危険性とその対策を学べる良い機会となるでしょう。
また、グループディスカッションの題材として使用することで、児童同士で意見を交わし合うことでさらなる学習となる効果が生まれます。
このプロセスを通じて、実際の状況での適切な判断力を育むことができるのです。
まとめ
「防災・防犯シュミレーション3」は、国崎信江氏が手がけた、家庭と学校での防災・防犯教育に欠かせない一冊です。
具体的なシナリオを通じて、子どもたちに現実に起こりうる危険を教えてくれるだけでなく、その対応を考えさせる良書となっています。
家庭では親子のコミュニケーションツールとして、また学校では教材として活用することで、子どもたちの危機管理能力を育むサポートをしてくれるでしょう。
この文化的かつ実用的な本を手に取って、皆さんもご家庭や学校で子どもたちと一緒に未来の安全を考えてみてはいかがでしょうか。
ショップ:楽天ブックス
価格:3,300 円
|
関連記事
防犯用ドア・窓チャイム「HSA-M4」のレビュー
日常生活を安心で包む、防犯用ドア・窓チャイム「HSA-M4」の魅力とは
日々の生活の中でセキュリティ意識を高めることは、多く... 防犯関連 |
自宅の防犯対策に新たな選択肢!大進の乾電池式センサーライトDLB-K500の魅力を徹底解説
毎日の暮らしの中で、安全を確保することは非常に重要です。
特に夜間や人の少ない場所では、防犯... 防犯関連 |
丈夫で安心な暮らしをサポートする透明フィルムの魅力
快適な暮らしを送るためには、住まいの安全性を高めることが重要です。
特にガラスの破損による被害を防ぐためには工夫が必要です。
... 防犯関連 |
セキュリティの第一歩!防犯カメラ作動中シールの効果とは
日常の安心を守るために、防犯対策は欠かせません。
そんな中で大きな効果を発揮するのが「防犯カメラ作動中シール」です。
初... 防犯関連 |
多様な用途に対応する!「グッズプロ」の泥棒警戒中のぼり旗を徹底レビュー
普段から商店やイベントスペースで見かけるのぼり旗。
その用途は多岐にわたり、その意匠は店舗やイベント参加... 防犯関連 |